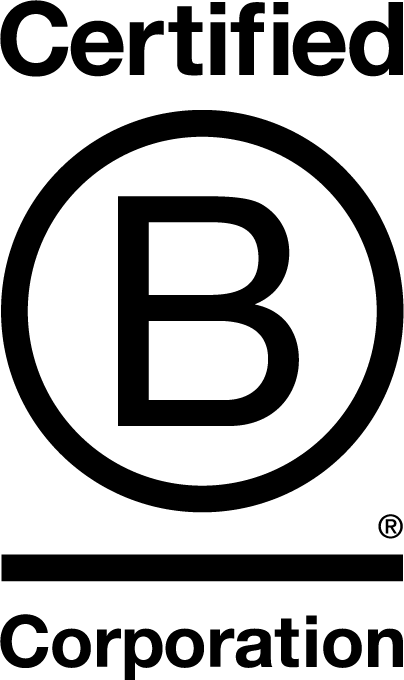Good Foodから考える水産業のあり方とは?
日本を代表する大手企業が一同に集まり、企業のCSRや持続可能性に対する取り組みを話し合う、サステナブル・ブランド国際会議が3月1日(木)、2日(金)の2日間にわたりヒルトン東京お台場にて開催されました。2017年に始まり、日本での開催2回目を迎える今回のカンファレンスには1500名以上の参加者が集まり、日本最大級の持続可能性に関するカンファレンスとなりました。
シーフードレガシーからは代表の花岡がゲストスピーカーとして参加し、Good Foodの観点から、サステナブル・シーフードについて紹介しました。
今回は、このサステナブル・ブランド国際会議2018の模様をレポートいたします!
2030年に向けてあるべきGood Foodを考える
~地球と人の健康が、ずっと続いていくFOODとは?~
ファシリテーター:
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会環境委員会副委員長 村上 千里 氏
パネラー:
ネスレ日本株式会社 マーケティング&コミュニケーションズ本部 執行役員 コーポレート・アフェアーズ統括部長 嘉納 未来 氏
味の素株式会社グローバル・コミュニケーション部CSRグループ長 長谷川 泰伸 氏
株式会社シーフードレガシー代表取締役社長 花岡 和佳男
企業にとってのGood Foodとは?
まずはネスレの考えるGood Foodについてを嘉納様がご紹介。チョコレートやコーヒーなど私たちの日常生活に深く関わる商品を提供するネスレにとって、同社のスローガンでもある「Good Food, Good Life」は消費者への約束であることを説明されました。消費者にとってのGood Foodとは「楽しく食べる事」であり、その環境づくりとして安心、安全、価格、そしてホッとできる空間を提供していくことが企業のGood Foodに関する取り組みに繋がる、と述べた上で、消費者の問題は企業や社会の問題でもあることを指摘されました。
続いて味の素株式会社の長谷川氏からは、同社の主力商品である調味料「味の素」にまつわるGood Foodについて。サトウキビを発酵させることで作られる旨味成分を原料としていることはあまり知られていません。味の素ではこの過程で発生するサトウキビの葉や搾りかすによるロスを防ぐ工夫を行なっているそうです。また農家に利益が還元される仕組みを導入するなど、生産の段階から消費者のGood Foodにつながる工夫をしています。長谷川氏は、全ての人が「美味しい、楽しい、嬉しい」ことがGood Foodにつながるとし、その一例とし、味の素が取り組むベトナムでの学校給食制度や教育支援について説明されました。
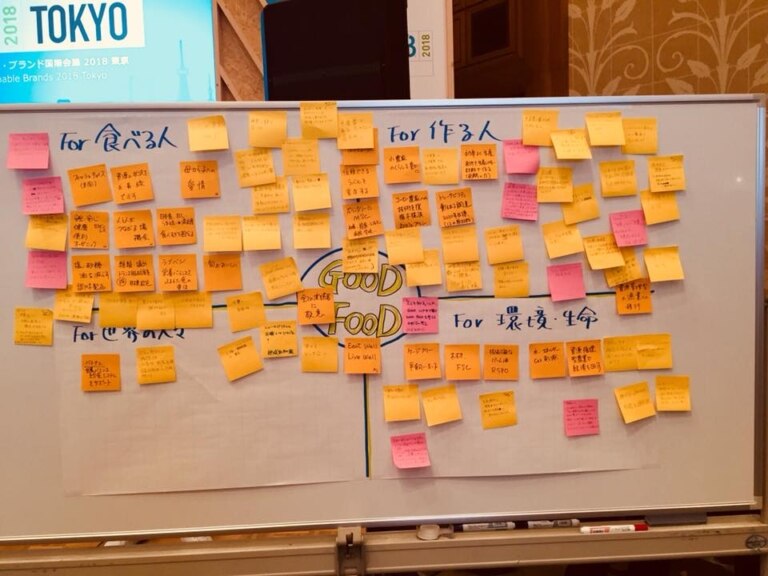
異なる視点から”Good Food”とは何か、参加者全員で考えるワークショップ形式のセッション。
水産業から考えるGood Food
そして最後にシーフードレガシーの花岡は水産業の視点からGood Foodについて説明。豊かな海を次世代に残す、という企業理念そのものが未来のGood Foodに繋がっているとし、世界の漁業事情について説明しました。日本では後継者不足や若者の魚食離れなど明るい話題の少ない水産業界ですが、世界的には成長産業であることはあまり知られていません。その背景には健康志向の広がりや日本食ブームがありますが、急速に広がる需要を満たすためにはきちんとした資源管理が欠かせません。欧米では過去の過ちから、現在では資源管理が徹底され、資源は回復傾向にあるものも多く、それと共にサステナブルシーフードのコンセプトも普及しつつあります。
日本は適切な制度のないまま漁業を続けた結果、日本周辺海域の水産資源は激減してしまいました。しかし、海外の事例に見るように適切な資源管理を行えば資源は回復するとし、漁業大国日本のポテンシャルの高さに期待をこめ、企業やNGOなどの専門機関が協働していくことの重要性を説明しました。
同じ時間帯にいくつかの分科会が行われる中、会場には多くの参加者が集まり、私たちの身近なトピックである「食」に対する関心の高さが伺えました。Good Foodを考える上で重要なのは、生産者から消費者までを繋ぐサプライチェーン全体を考えること。IUU漁業に関与した水産物や、児童労働や強制労働によって収穫されたカカオなどは、もちろん消費者にとってもGood Foodとは言えません。消費者の私たちには商品を選ぶ自由がありますが、それは同時に商品を選ぶ責任でもあることが、パネルディスカッションでハイライトされました。また、こうしたサプライチェーンを通しての課題は企業が単体で取り組んでも実現が難しいため、企業、NGO、専門機関など多様なステークホルダーが協働していくことが不可欠であることを再確認するセッションでした。